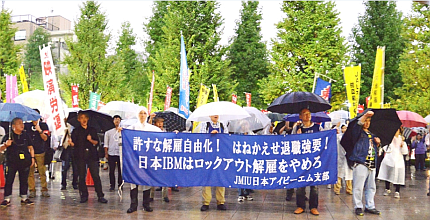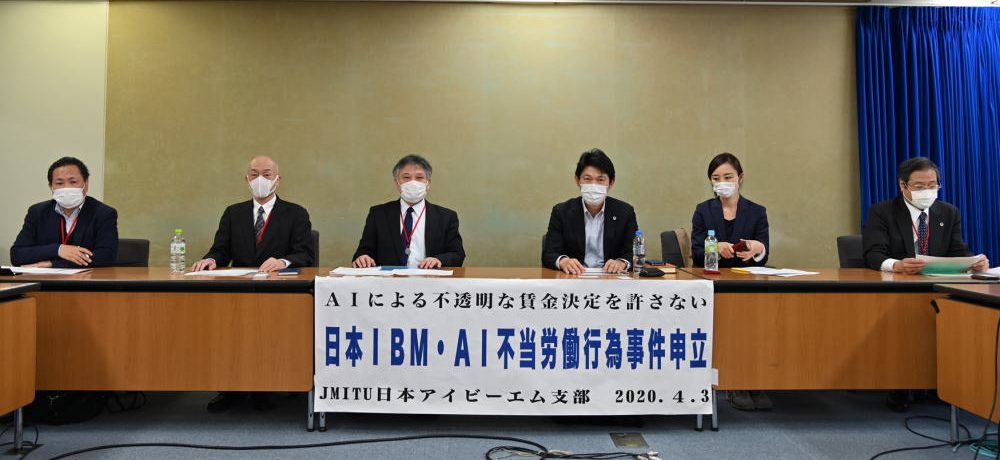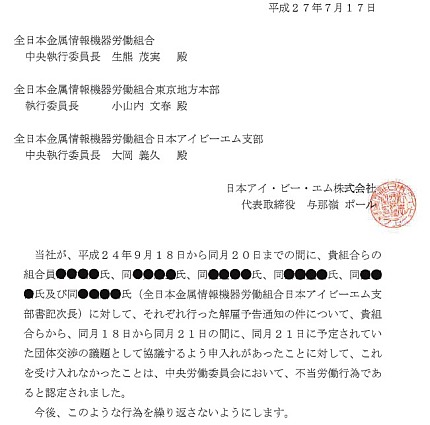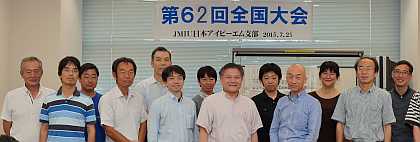ラインによる障害者虐待防止法違反の疑い
担当、フレックスタイム認めず -第21回団交報告-
6月18日に団体交渉を行いました。その中から障害者虐待防止法、裁量勤務制度、フィットネス・ジム、賞与発表の注意事項文言、RAについての協議内容を以下に報告します。
ラインによる障害者虐待防止法違反の疑い
GTS・リスクマネジメント部門のT担当は、視覚障害者の部下がラッシュアワーとなる危険な時間帯の通勤を避けるためフレックスタイムを利用して10時出社を希望しているにもかかわらず、それを認めようとしないため、団体交渉でこのことを協議しました。
組 この部下が証拠の残る形で10時出社が希望であることをメールでT担当に伝えたところ、T担当はなぜかこの部下を面談に呼び出して口頭で何か特殊な条件をつけた上で10時出社を認めた。さらに、その内容ついて議事録を書くように指示し、あろうことか、「当職の認識と大きく乖離している場合は取り消すこともある」などとこの部下を脅迫したことがわかった。就業規則で認められているフレックス出社に何か特殊な条件をつけることは差別的な扱いを意味し、労働基準法に照らして問題だ。さらに、脅迫するなどということはあるまじきことで、障害者虐待防止法の適用も視野に入れている。これ以上T担当が不適切な言動を行わないよう対策することを要求する。
会 回答は準備中だ。
組 なぜ面談なんかするのか。もっとシンプルにメールへの返信で「了解しました」と返せばいいだけだ。
会 10時出社は認めている。この件について調査する。
シフト勤務なのに裁量勤務制度を適用
組 社員の労働条件に変更がある場合は事前に社員に説明するべきだ。なんの事前説明もなしにいきなり裁量勤務になった社員がいる。しかもこの社員は現在プロジェクトでシフト勤務についている。シフト勤務であれば勤務時間の裁量がないため、裁量勤務制度を適用するのはおかしい。きちんと説明してほしい。
会 確認調査する。
組 速やかに対応しないと労働基準法違反になる。さらに、この社員だけの問題でなく、同じ職場の人全体の問題だ。対象者が何人なのかも調査してほしい。
会 特殊なケースなので調査する。
組 もしもラインの暴走だったら厳重注意してほしい。
会 より深く事実を調査する。
賞与・定期俸制度の発表にある注意事項は労基法違反
組 5月1日付賞与・定期俸プログラムについての発表の一番下にある「注意事項」の文言に、「IBMが本件プログラムによる支払いを行う、維持する、または継続する義務や約束をするものではありません」との文言があるが、これは労働基準法に照らして問題だ。そもそも賃金や労働条件については労使対等の立場で協議し、合意のもとで実施されるべきものだ。
会 この注意事項は今回から入ったものではなく、昨年の3月11日付発表から入っている。
組 この注意事項は昨年冬の賞与時には無くなっていた。そしてこの春にまた復活した。
会 一方的に賞与を廃止することはない。
組 それならこんな注意書きは不要だ。労働条件は労使対等原則で決まるものだ。英文をそのまま訳すのはやめて欲しい。
会 持ち帰って検討する。
フィットネス・ジムの件
組 箱崎事業所にフィットネス・ジムを作る件はその後どうなったのか。
会 場所についてはほぼきまったようだが、まだ内容についてはお話しできる段階にない。
組 場所はだいたい箱崎のどのへんということは決まったということか。
会 まだアナウンスできる状態ではない。箱崎の中もまだ改装が続いている状態だ。運用についてもこれからだ。
RAは休職者を狙い撃ちか
組 RAの部門予算などについては回答しないという回答だが、それでは協議できない。回答を要求する。RA対象となった理由も不十分である。
会 部門予算について回答する考えはない。今後のキャリアを考えて欲しい人に声をかけている。
組 声をかけるのは休職者も対象か。
会 休職理由によるが上司の判断で声をかけることはある。
組 退職を提案するなら、理由をきちんと説明するべきだ。予算なども全体像を示して欲しい。もう少し情報を開示して欲しい。
会 要求はわかった。