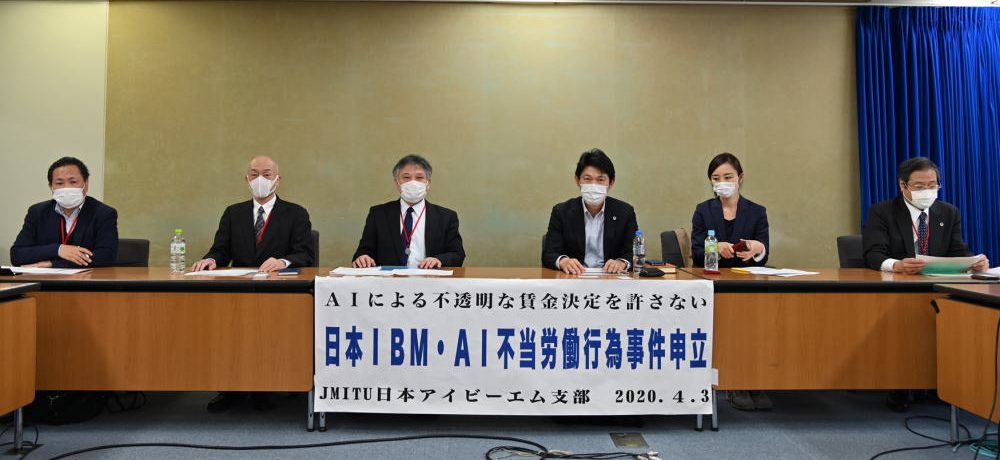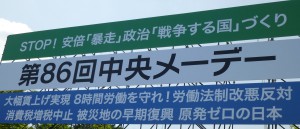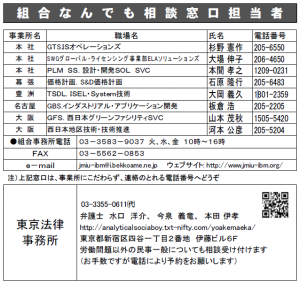ロックアウト解雇は無効
-ロックアウト解雇の本質は整理解雇-
5月12日、第四次ロックアウト解雇裁判の口頭弁論が東京地裁で開かれ、原告訴訟代理人の意見陳述が行われました。以下に、訴訟代理人の意見陳述書を掲載します。
意見陳述書
2015年5月12 日 原告訴訟代理人 弁護士山内一浩
1 本件解雇が、米国IBMの指示によるSO業務部人員削減のための整理解雇であることは、本件解雇直前の面談時の吉井豊氏の発言から明らかです。本件ロックアウト解雇の前の2014年2月21日午前10時から10時15分まで、吉井氏は原告と面談しました。そのなかで吉井氏は、
① 米国IBMの指示・命令として、SO業務部の「本土」チーム(幕張チームのメンバーの他にA氏の勤務する大阪、B氏の勤務する福岡のメンバーを含む)の人員と沖縄・大連チームの人員の比率を、「昨年の20%対80%」から、15%対85%と本土の比率を下げる方針が出されている。これにより、「本土」チームのさらなる人員削減が必要になる。
② この人員削減の方針は、同年2月18日に米国IBMの担当副社長から被告に伝えられ、その後私に伝えられた。米国IBMとしては、同年半ばにはこの人員削減を達成せよ、とのことであった。
③ SO業務部としては、この方針を達成するにはさらに業務を沖縄や大連チームにシフト(移管)する必要があるが、部分的にシフトするのは却って問題があるので、SO業務部のほぼすべての現業を沖縄チームにシフトさせることに決定した。
④ そのような「背景」の中で、同年3月末日(同年第1クォーター末)を退職日とする早期退職プログラムが実施されることになっている。原告がこのプログラムを利用するかどうか検討してほしい。
つまり、吉井氏は、米国IBMからの「本土」チーム人員削減の方針が示されたことから、原告に対して早期退職プログラム(RAプログラム)を「利用」した退職を「勧奨」してきたのです(なお、米国IBMは、2014年第1クォーター(四半期)において、全世界での「人員再調整費用」として8億7000万ドルを支出していた)
原告は、3月5日、この退職「勧奨」を拒否する旨を吉井氏に伝えました。被告は、それからわずか5日後の3月10日、原告に対して同年3月28日付で解雇する旨の解雇予告の意思表示を行いました。
また、同年3月末(同年第1クォーター末)には、やはりSO業務部幕張チームのC氏、D氏も、吉井氏のいう米国IBMからの「本土」チーム人員削減の方針により、退職勧奨を受けて早期退職しています。
この吉井氏の面談時の発言、そして2012年も2013年も、SO業務部において原告の他に早期退職した社員が何人もおり、現在では旧SO業務部の業務を担当している社員はわずか2名に減らされていることなどから、本件解雇は、米国IBMの指示・命令によるSO業務部(本土)の人員削減方針を実現するための整理解雇であることは、もはや明確です。
2 こうした大量の人員削減は、全世界のIBMにおいて行われていることであり、例えば昨年度第1四半期の間においても、IBMはインドやブラジル、欧州各国など世界中で約1万5000人を解雇する計画を立てており、米国内やインドにおいて既に大規模な人員削減に着手している。また米IBMは、2013年からの2年間にフランスで最大1400人を削減する計画をフランスの労働組合に通告しており、実際IBMフランスにおいては、大規模な人員削減が実施されています。
そして、日本においても、被告は米国IBMの指示・命令に従って人員削減を繰り返し行ってきており、SO業務部(本土の幕張チーム)では、2013年6月末にE氏、F氏、G氏の3名が退職勧奨を受けて早期退職し、上記のとおり2014年3月末にはC氏、D氏も退職勧奨を受けて早期退職し、かつ退職勧奨を断った原告は解雇されました。現在SO業務部は他の部署に統合され、その結果、現在旧SO業務部の元幕張チームとして残っているのは、H氏とI氏の2人だけです。よって、原告の能力不足、業績不良なる「解雇事由」は、人員削減のための整理解雇の本質を隠蔽するための口実に過ぎないと思料します。
3 関連訴訟における被告証人の証言も、一連の解雇が能力不足解雇ではなく整理解雇であることを裏付けています。関連別訴である1次訴訟の原告の上長であった川喜多克郎氏は、「2012年9月(同年第3クォーター末)20日に原告への解雇予告通知がなされたが、原告が解雇されることを川喜多氏が知ったのは、その解雇予告の数日前であり、被解雇者が原告であることは、人事部門の方から通知してきた」と証言しています。
真実、原告が、もはや職場に残しておけないほど業績が著しく不良で解雇もやむなしと言うのであれば、原告を解雇すべきことは、原告の勤務状況や業績等をよく知る現場の上長である川喜多氏の方から人事に上申していたはずです。
ところが、事実は、現場の川喜多氏の方から原告を解雇するよう上申したのではなく、人事部門が決定し川喜多氏に連絡してきたのです。このことからすれば、被告は、RAプログラムを含む人員削減計画を立て、それを実行する中で、RAプログラムに応じた社員についてはその適用を認めて合意退職扱いとしたが、RAプログラムに応じない原告らについては解雇を強行したという構図は明白です(なお、米国IBMは、2012年第3クォーターにおいて、全世界での「人員再調整費用」として4億8000万ドルを支出した)。
よって、本件解雇を含むこの間の一連の解雇が、真実は能力不足や業績不良を理由とする解雇ではなく、人員削減のための整理解雇であることが明らかです。
4 しかし、本件解雇は、多言を要するまでもなく整理解雇4要件をいずれも充たしていません。経営上の高度の必要性の有無1つをとっても、被告の2013年度の業績は売上高8804億6500万円、経常利益は973億1700万円であり、経営上の高度の必要性などまったく認められません。よって、本件解雇は無効です。
裁判所におかれましては、本件解雇の真相を理解され公正な判決を下されるようお願い致します。