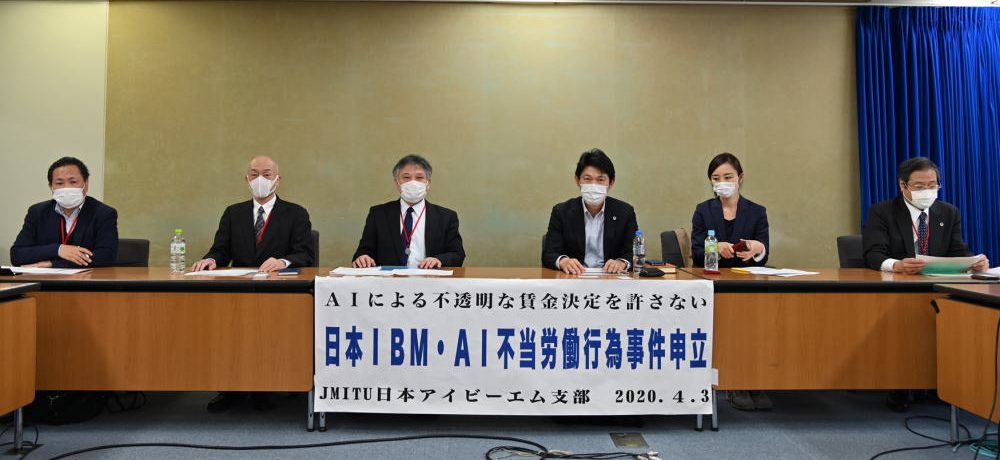ILO(International Labor Office:国際労働機関)が提案する「働き方」、「ディーセント・ワーク」について、組合員からの投稿にてご紹介します Read more
「ディーセント・ワーク」とは?――家庭も大事にしながら女性の社会参加の機会を
職場から寄せられたリストラ不安視の声 業績目標の未達成で大幅なリストラが現実味を帯びる
日本アイ・ビー・エムは主要国の中で唯一、目標が未達成だったことから、またぞろ、リストラが実行に移されるのではないかと社員の間で不安が広がっています。
その不安が真実ではないかと思わせる次のような報告が組合に寄せられました
2009年度日本IBM組合中央執行委員会書記長になりました。
こんにちは、このたび中央の書記長となりました渡辺です。団塊の世代が定年退職していく年に、重責を担うのは結構大変ですが、だれがやってもその人なりにやれるし、足りなければ周りが補ってくれるはずです。そして、今までどおりは、やりたくてもやれないし、むしろ変わらないといけないと思います。IBMグループで働く人たちの視点で、やれることはやっていきたいと考えています。
ここが問題・HDD部門分割・売却(その1) いままでの判決と最高裁への上告理由
2002年12月の「会社分割法」「労働契約承継法」に基づく日本アイ・ビー・エムからのHDD部門の分割、そして6日間のちに日立製作所へ売却、という事態から五年半。横浜地裁・東京高裁での不当判決を経て、日立GSTで働く9人の組合員は、この問題を最高裁判所に上告しています。
「かいな」では、3回に分けて、原告お呼び弁護団の主張を、できるだけわかりやすく、図表を使いながら解説していきます。
表1 上告理由の要旨
| 項目 | 内容 |
| 「承継拒否権」の「解釈誤り」と、「会社分割法制」の「合憲的限定解釈(=注1=)」 | 憲法第22条第1項(職業選択の自由)、第27条第1項(勤労の権利)などに照らして、労働者側に一方的に不利な解釈をしている。 |
| 「適用違憲(=注2=)」の問題 | 「商法等改正法附則」第5条に定められた「個別協議」において、説明義務が十分に果たされていないため、民法第625条第1項に定められた「移籍時の従業員の同意原則」および憲法上の職業選択の自由を制約できるための適用条件を満たしていない。 |
今回は、「上告理由書」の内容を踏まえて、その理由のひとつ、「職業選択の自由」に関する論点を見ていきます。
「職業選択の自由」をどう考えるのか
表2 「職業選択の自由」に関する解釈の違い
| 労働契約承継時 | 退社する自由 | 分割もと会社に残る自由 |
| 地裁・高裁判決 | ○ | × |
| 原告・弁護団 | ○ | ○ |
地裁・高裁判決は、ともに「労働契約承継」によって設立会社等(=分割された方の会社)に承継された労働者は、「退社(=退職)の自由」はあるが、分割会社(=分割もとの会社)に残ることは認められない」としています。
しかし、これは憲法第22条第1項に定められた「使用者の選択の自由(=職業選択の自由)」を制限するものであり、労働契約承継を伴う会社分割に先だって行われる個別協議においてこれを承諾しなかった(=承継拒否権を行使した)者については「退社の自由」しかない、とするのは憲法第27条第2項に定められた「勤労(労働)の権利」の保障義務に違反する(すなわち「違憲」)である、というのが私たち原告の主張です。
そして、上告理由書においては、労働者が担当していた業務が他社への分割により存在しなくなることから、配転や整理解雇のリスクを念頭に置いて承継を拒否した労働者に対しては、整理解雇はその「解雇四要件」に照らして行われなければならず、日本アイ・ビー・エムにあってはこの解雇四要件を満たさないため当然「配転」によって対処されるべきだ、としています。
表3 「整理解雇の四要件」
| 要件 | 解説 |
| 人員整理の必要性 | 人員削減をしなければ経営を維持できないほどの必要性があるのか? |
| 解雇回避努力義務の履行 | 他のあらゆる手段について検討を尽くしたのか? |
| 被解雇者選定の合理性 | 解雇するための人選およびその基準は合理的で公平だったのか? |
| 手続の妥当性 | 当事者の納得が得られるまで説明・協議を尽くしたのか |
次回は、もうひとつの論点である「従業員の同意なしでの移籍」を認める条件について、ならびに高裁判決で新たに提示された「不利益当然甘受論」など今後の同様案件に影響を及ぼす論点を見ていきます。そして三回目は、「会社分割」「労働契約承継」を認める悪法をやめさせる取り組みについて述べます。
注1 : 法律適用の前提となる法律解釈が一義的に決定できない場合で、かつ、当該法律が違憲となる解釈が存在するような場合に、これを合憲的に解釈する解釈方法。言い換えれば、「普通に解釈したのでは違憲になりかねない法令なので、適用時には違憲にならないように(限定的に)解釈すべきである」という論理。
注2 : 法令自体は合憲であるが(※上告理由書上では「~であったとしても」)、その法令を当該事件の当事者に適用する限りにおいて違憲とするもの
職場ミニ通信:1stラインにも転籍強要
箱崎事業所の方から投書をいただきました。
スタートした新体制 生活・健康・雇用を守る闘いを継続/橋本雄二 新委員長
読者の皆さん、こんにちわ。組合は、全国大会を7月に開催し、新役員を別表(※このサイトではまだ未公開)のとおり選出しました。
新役員を代表して新年度の組合方針を簡単に説明させて頂きます。
IBMコーポレーションの08年2Qの業績はすばらしいものでしたが、日本IBMの業績は、国内の競合他社が堅実な成長を遂げている中で、メジャーマーケットの主要国の中で唯一、目標が未達成となりました。今後は昨年10月に設立されたJapan IOTの締め付けがきつくなることが予想され、人減らしリストラ策が即実施されることは間違いありません。既に3Qの業績回復に向けて水面下では陰湿な退職強要が推し進められているようです。
一方、みなさんの我慢の限界をこえているのが「ゼロ昇給」ではないでしょうか。以前からそうでしたが、特に05年10月に発表された「人事改革」以降は猫の目のように毎年しくみが変わり、それにともない格差は毎回拡大されています。PBC2の評価で「ゼロ昇給」ではたまったものではありません。組合が6月に実施した賃金調査結果では今年も約4割の人がゼロ昇給、3年連続ゼロ昇給の人は2.5割にも達しています。またゼロ昇給については7割以上の人が「問題あり」と異議をとなえています。
制度改悪で毎年年収が下がる人も多く、将来設計もままならない状況もうまれています。
このような状況の中で組合は7月19日に第55回全国大会を開催し09年度の方針を次のとおり決定しました。
その一つは成果主義とのたたかいです。昇給制度、給与調整制度の見直しをはかり誰でもが賃上げを勝ち取ることです。また、賃金の格差拡大と個人間競争をあおる成果主義賃金を是正させ、誰でもが納得できるガラス張りの賃金制度の確立を会社に要求していきます
二つ目は健康で働ける職場を作ることです。裁量労働制の適切な管理を実施させ、「サービス残業」をなくしていきます。ILOが提唱している人間らしい労働「DECENT WORK」をめざしていきます。
三つ目は雇用を守るたたかいです。グローバル化により日本IBMの労働者は職場を失い、またこれまで培ってきたスキルを活かせない苦境を強いられています。このような人たちに対し「業績改善プログラム」が実施され、パワーハラスメントによる降格人事や退職勧奨が横行しています。人間の尊厳を損なうこのような制度は即撤廃させ、まっとうな仕事を確保させていきます。
私たちは少数組合ではありますが、健康で明るい職場、そしてリストラのない職場を目指し頑張っていきますので今後とも多くの方々のご支援よろしくお願いいたします。
【多くの支持にお礼申し上げます】健康保険組合互選議員補欠選挙・投票結果
8/25(月)に行われた健康保険組合互選議員補欠選挙の投票結果をお知らせいたします。
投票総数 1,308(郵便投票 379、直接投票 929)
有効投票数 1,295(郵便投票 372、直接投票 923)
各候補の得票数
長谷川 昇 377(郵便投票100、直接投票277)
当 (相手候補) 918(郵便投票272、直接投票646)
おかげさまで組合推薦候補である長谷川さんは、直接投票では3割、全体でも29%の得票(有効投票数比)を売ることが出来ました。皆さまの多数のご支持に改めて感謝申し上げます。
今後とも組合では、健康保険組合の健全運営に対し、団体交渉などを通して意見を具申して参りますので、引き続き皆さまのご支持をよろしくお願い申し上げます。
健康保険組合の運営に関するご意見・ご感想も、メールフォームからお気軽にどうぞ。
【いよいよ投票日】健康保険組合互選議員補欠選挙
8/25(月)は健康保険組合互選議員補欠選挙の投票日です。「開発・製造部門」の方は忘れずに、そしてぜひとも労働組合推薦の候補に、投票してください。よろしくお願い申し上げます。
退職強要にご注意を――ソフトウェア事業での実例
ソフトウェア事業所属の方から以下のような報告を受けました。
【解説】 「健康保険組合互選議員選挙」とは
8月25日(月)は、「開発・製造部門」の「健康保険組合互選議員選挙」の投票日です。
……と言われても、皆さんの生活にどう影響するのかわからない、とおっしゃる方もいらっしゃるかも知れません。そこで、「健康保険組合互選議員選挙」の意義と、なぜ労働組合は立候補者の推薦をするのか、を簡単に解説します。